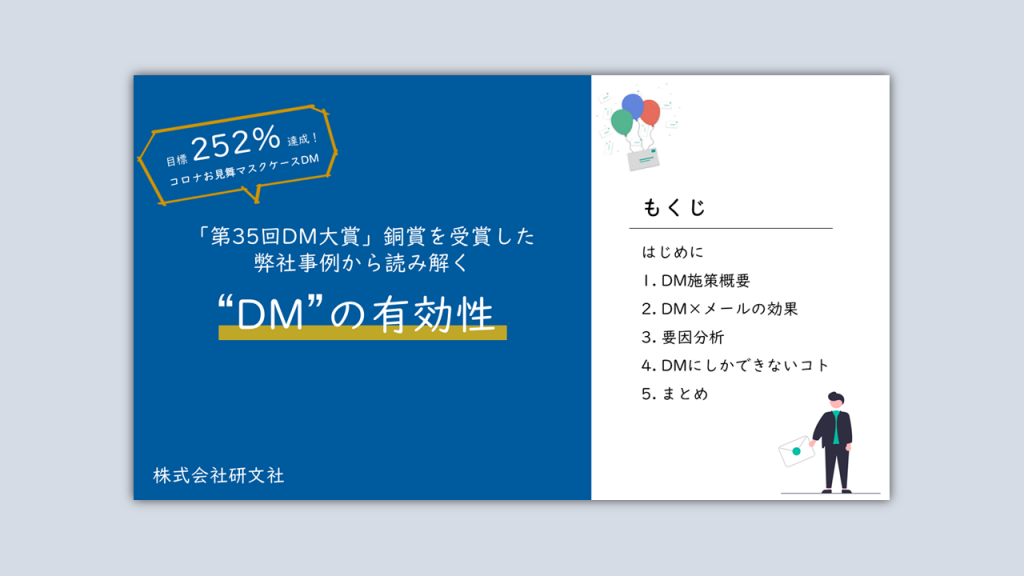ダイレクトレスポンスマーケティング(Direct Response Marketing)とは簡単に言うと、商品の販売をスムーズにするマーケティング手法の1つで、飛び込み営業などのプッシュ型の手法ではなく、レスポンスがあった顧客をターゲットとしているため、効率的に優良顧客を獲得しやすいなど、とても魅力的なマーケティング手法です。
本記事では、ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組みや歴史、具体的な手法、メリットとデメリットなどをご紹介します。
- プッシュ型のマーケティング・営業スタイル中止で頭打ちになってきている
- 売上に繋がる効果的なマーケティング手法を知りたい
- ダイレクトレスポンスマーケティングをしっかりと理解したい
このようにお考えの方は参考になるかと思うので、ぜひご覧ください。
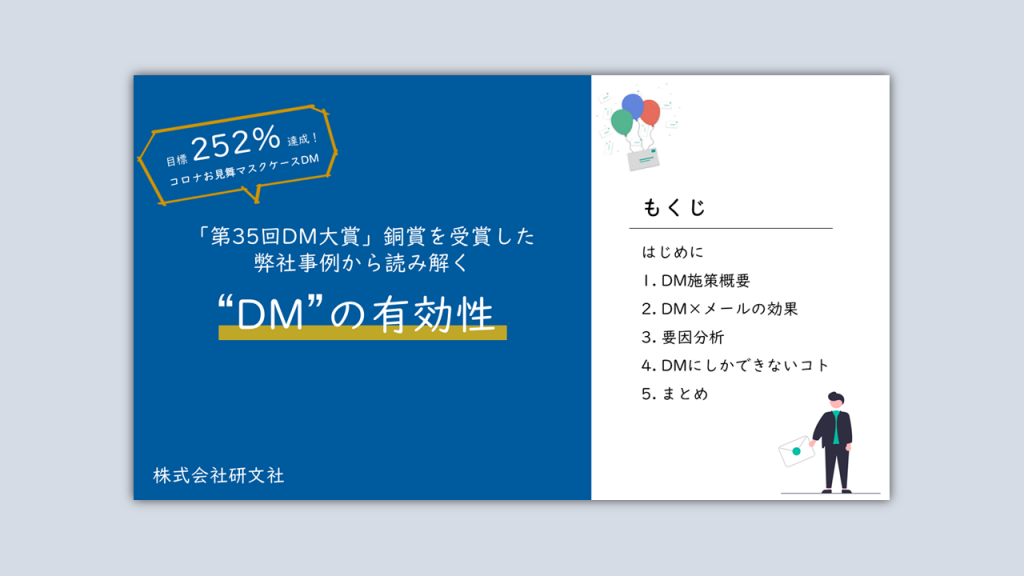
目次
ダイレクトレスポンスマーケティングとは?
ダイレクトレスポンスマーケティングとは、 広告やプロモーションに対して興味を持ちレスポンスがあった顧客に対して直接サービスや商品を販売する手法を言います。
ダイレクトレスポンスマーケティングが誕生したのは1920年代にアメリカの企業が、新聞広告などを利用して商品の情報を流し、顧客からの購買アクションを待つという手法を導入するようになりました。
仲介業者や実店舗を通して商品を売買するのが主流だった当時、この手法は画期的で、それ以降見込み顧客の興味を引くための言葉選び、特典や保証などのアプローチ方法が考案・研究されるようになりました。
その後日本で普及し始めたのは1998年頃と言われており、当時は中小企業を中心にダイレクトメール(DM)やニュースレター、テレアポなどが導入されはじめ、今では通信販売企業のジャパネットたかた、健康食品会社のやずやなどの大手企業も活用しています。
また、通販会社だけでなくインターネットとの相性もいいこともあり、注目度を増している手法です。
ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組み

ダイレクトレスポンスマーケティングは、主に集客・教育・販売の3ステップから成り立っています。それぞれ詳しく解説します。
STEP1:集客
まず第一段階で行うのは、 見込み顧客をターゲットとした集客=見込み顧客のリスト化を目指します。
具体的に何をするのかというと、見込み顧客に対して、価値があると思えるような有益な情報を提供し、対価として顧客情報の獲得を目指します。
例えば、Webサイト上で無料サンプルの配布や資料請求、役立つレポート資料の提供、DMでセール情報や期間限定商品のお知らせなどです。
この集客無くして販売はないため、集客の母数が大きいほど売上も比例して大きくなる可能性が高くなるため、非常に重要な部分と言えます。
STEP2:育成
続いて行うのは見込み顧客の育成ですが、ここで言う育成とは、信頼関係の構築や顧客に対する継続的なアプローチのことです。
例えば、会員限定の特典を用意したり、顧客にとっての有益な情報を定期的に発信したりするなどが該当します。他にも、顧客からの問い合わせに対応したり、アンケートを取ったりすることも挙げられるでしょう。
集客した見込み顧客はいきなり自社のサービスや商品を購入するなどの行為に至ることは少なく、あらゆる情報を取捨選択しながら購買行動を行います。
その顧客の購買行動のプロセスの中で自社を選んでもらうためにも、自社に対する信頼度を高め、顧客が自社のサービス・商品を利用したくなる機会を増やすための育成が必要不可欠となります。
■関連記事:リードナーチャリングとは?概要から手法までわかりやすく解説!
STEP3:販売
集客・教育ができれば、次は販売です。
顧客は先述した育成によって自社のサービスや商品を理解・信頼し、購買意欲が高まっている状態なのでスムーズに販売が行えます。
しかし、ここでもただ販売するのではなく、顧客のニーズをしっかりと考えることが大切です。
例えば、通販であれば期間限定の特典を付けたり、分割払い対応にしたり、クーリングオフなどの保証を付けたりしましょう。
そうすることで販売に繋がる可能性が高まるだけでなく、更なる信頼を得られるためリピート率向上へとつながるでしょう。
ダイレクトレスポンスマーケティングの主な手法5つ

ここでは、ダイレクトレスポンスマーケティングでよく使われる具体的な手法を5つ紹介します。
Web(インターネット)
今では会社規模問わず、ほとんどの企業がWebを活用しているかと思います。Webだけでもあらゆる手法があり、ブログを含むオウンドメディアやWeb広告、メディア広告などで集客し、見込み顧客からのレスポンスがあったら育成・販売をしていくという流れです。
日頃からWebでの検索や調べたりすることが当たり前だからこそ、Webでの接点が重要になるため、まず着手すべきダイレクトレスポンスマーケティングの手法の1つです。
■関連記事:Webマーケティングとは?施策の種類や始め方、必要なツールをわかりやすく解説!
DM(ダイレクトメール)
代表例としてチラシやカタログなどを用いたDM(ダイレクトメッセージ)が挙げられます。
DMをオススメしたいのが、在宅していることの多い専業主婦や高齢者などがターゲットの場合で、購入したことのある企業のダイレクトメッセージは、93%の確率で開封されているという調査結果が出ています(「DMメディア実態調査2021」より)。
サービスや商品を利用したことがある顧客には積極的に送ると良いのはもちろん、BtoBにおいても、直接決済権のある社長や役員宛に、費用対効果の面や課題解決が出来るような内容の訴求軸でのDMも効果的でしょう。
■関連記事:ダイレクトメール(DM)とは?メリット・デメリットや効果をアップさせる方法も解説します!
電話やEメール
電話やEメールを使った手法もダイレクトレスポンスマーケティングではよく使われおり、一般的にはBtoCよりも、電話やEメールに慣れ親しんでいるBtoBに向いています。
電話は時としてクレーム対応が発生する場合もありますが、基本的には直接的に顧客とやりとりができるため顧客からの信頼関係を築きやすいでしょう。
Eメールでは、育成での役立つ情報の提供、顧客が購入した後のお礼、誕生日のお祝い・特典に関するメッセージを送るのに効果的です。あまり費用も手間もかからない、手軽な手法と言えます。
ただし、電話やEメールは間接的なやりとりになるため顧客の離脱率も高くなる点に注意しましょう。
電話では、顧客の興味度合いの状況によっては“押し売り”に聞こえることもあり、印象が悪くなり離脱する可能性が出るケースもあることや、Eメールでは、メールマガジンでセールや期間限定の情報を発信したり、顧客の関心が高まる傾向にあるタイミングを見計らってステップメールを送ったりと、こまめな対策が必須です。
■関連記事:BtoBメルマガを成功させる方法とは?作成時や工夫のポイントを解説
SNS
みなさまの周りでも「あの企業もSNSやってるんだ」なんて思ったことあるのではないでしょうか。そんなSNSはダイレクトレスポンスマーケティングの中でも注目の手法です。
X(旧:Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNS上で見込み顧客へ情報を発信したり、問い合わせ対応をしますが、中でも特筆すべきは“直接コミュニケーションを取れる”という点で、SNSの大きな優位点と言えるでしょう。
企業がSNSを取り入れることで、
- 直接的な接点を増やしファン化につながる
- 購買行動の際に「商品を買うなら(サービスを使うなら)SNSでよく見るこの会社の商品(サービス)にしてみようかな!」と選択肢に入る
など、売上につながる可能性が見込めるため、今や注力している企業も珍しくありません。
ダイレクトレスポンスマーケティングの一環でSNSに取り組む際は、炎上には十分に気をつけながら、ユーザーが興味をそそられるようなコンテンツの投稿をしていきましょう。
レコメンデーション
レコメンデーションはECサイトでよく使われている手法で、ECサイトを運営されている方や、よくECを使う方は馴染み深いのではないでしょうか。
ECサイトを見ていると「あなたにオススメの商品」と表示されているのを見かけたことはありませんか?まさにこれがレコメンデーションで、顧客が実際に購入してきたものや検索履歴などを基に、その顧客に合った商品情報を表示する仕組みのことを言います。
顧客に電話やメールなどを送らなくても、顧客が関心を持ちやすい商品を自然に目立たせることができるという点が魅力で、しつこく強引な印象が薄いため、顧客はその商品情報を受け止めやすいでしょう。
レコメンデーションの活用はECサイトだけでなく、Webメディアや求人サイトなどでも活用できるので、まだ実装していない企業はぜひレコメンデーションを活用してみましょう。
ダイレクトレスポンスマーケティングのメリットとデメリット
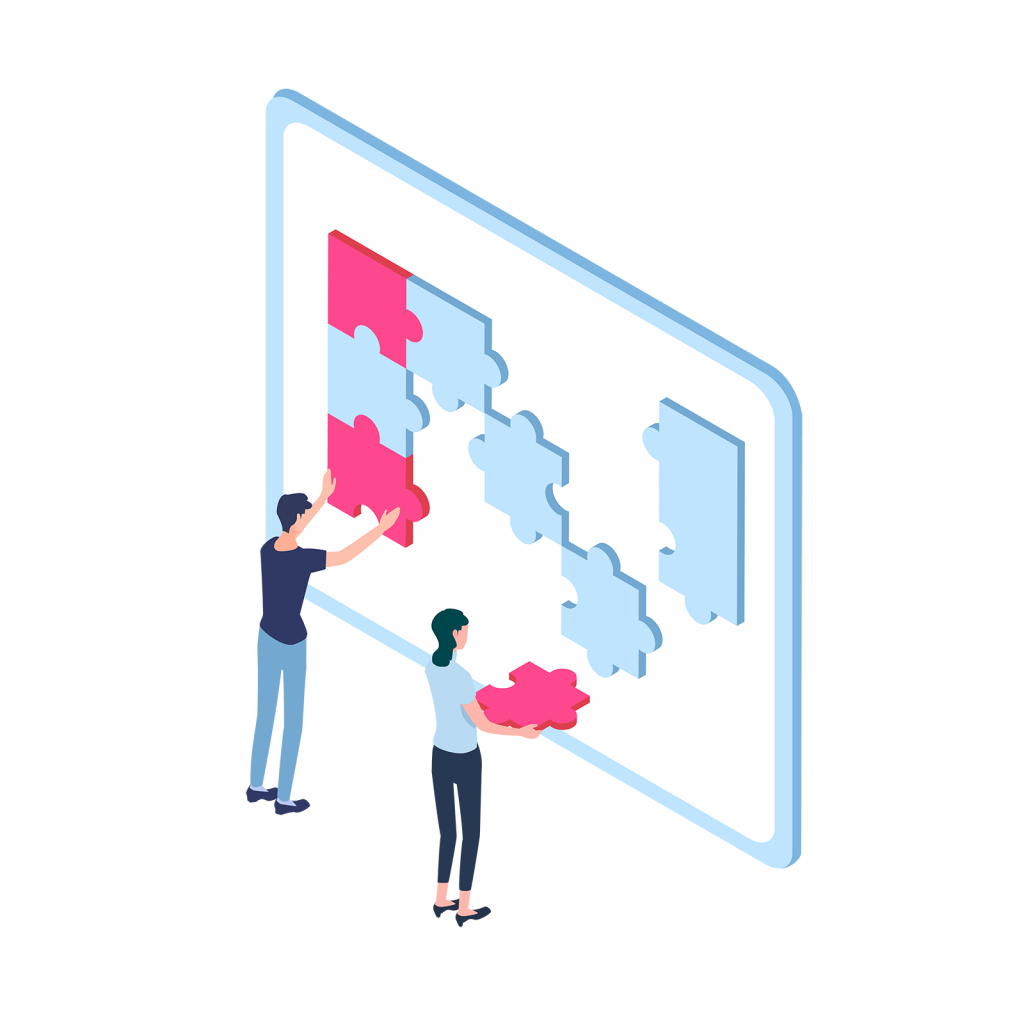
ダイレクトレスポンスマーケティングを導入する際は、メリットとデメリット両方あることを理解してくことも必要不可欠です。ダイレクトレスポンスマーケティングの成功させるためにも、ここからはメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット①:購買確度の高いユーザーのリストが作れる
1つ目は、購買確度の高いユーザーのリストが作れることです。
見込み顧客側からのレスポンスがあるということは、能動的に行動をしているわけなので、こちらからプッシュしていく手法に比べ、興味や購買確度の高いユーザーである可能性が高いです。
そのため、購買確度の高いユーザーのリストが作れ、ひいては効率的に優良顧客を獲得できます。
メリット②:少額の費用でも成果を得られやすい
2つ目は、少額の費用でも成果を得られやすいことです。
色々なメディアに広告を出すのではなく、特定のターゲットに向けてのみ情報を発信するため、広告・宣伝費が抑えつつターゲットが絞られるので成果を得られやすいです。
また、見込み顧客がレスポンスを起こしてからのみ営業活動が発生するため、人件費も最小限にできるでしょう。
メリット③:顧客分析がしやすい
3つ目は、顧客分析がしやすいという点です。
顧客獲得にかかったコストや、サービス・商品の販売成功率、レスポンス率などを数値化することができて、顧客の傾向を分析しやすくなります。
これらを分析することで、効率的に今後の改善点や具体的な対策を練ることができるでしょう。
メリット④:Web(インターネット)との相性が良い
最後は、Web(インターネット)との相性が良いという点です。
Webサイトなどのインターネットでの情報発信やWeb広告を行うことで、24時間365日商圏関係なく、いつでも顧客からのレスポンスを得ることができます。
また、Webサイト上にフォームを設置し、顧客自身に氏名・住所・メールアドレスを入力してもらうことで、見込み顧客のリスト化も簡単にできます。
デメリット:急を要する商品には不向き
メリットの多いダイレクトレスポンスマーケティングにも、デメリットが1つあります。
それは、急を要する商品の販売には向いていないということです。
具体的には、壊れた家電や水漏れなどの修理サービスなどが挙げられます。ダイレクトレスポンスマーケティングは、特定の顧客にのみ対応していく手法であるため、これらの商品には向きません。
また、この手法は育成という過程を踏みながら長期的に顧客へアプローチをかけていくものなので、即効性が重要となるサービス・商品には、別の手法を検討する必要があります。
ダイレクトレスポンスマーケティングが向いているサービス・商品

ダイレクトレスポンスマーケティングに向いているのは、顧客にとって馴染みがなく、不信感を抱かれやすいものが向いています。例えば、
- 高価な商品・サービス(高単価商品)
- 自社でしか販売していない商品
- 流行する前の商品・サービス
などを中心にダイレクトレスポンスマーケティングが活躍します。
なぜ上記のようなサービスや商品が向いているのかというと、ダイレクトレスポンスマーケティングは先述の通り、時間をかけて顧客を育成(教育)していく要素があるからです。
上記のような商品やサービスは、いきなりセールスしても買ってもらえる可能性は低いですよね。
そこで「育成」を行い信頼関係を構築していき、商品やサービスの価値や必要性を感じてもらった上でセールスを行います。
そうすることで、ただ単純にセールスするよりも、顧客が納得した状態でセールスを行えるため、上記のような商品・サービスでも効果的に販売していくことができます。
もし、上記のような顧客へ販売するハードルが高いサービス・商品を扱っている方は、ぜひ活用を検討してみましょう。
まとめ
ダイレクトレスポンスマーケティングは、商品の販売をスムーズにするマーケティング手法の1つで、集客・育成・販売というステップがあり、こちらから一方的に売り込むプッシュ型ではなく、レスポンスがあった顧客に対して販売を行うため、効率的な売上UPや優良な顧客獲得が見込めます。
そして、特に通販や高単価商材、市場的にまだあまり馴染みがないサービスや商品が、ダイレクトレスポンスマーケティングに向いており、もし貴社が上記に当てはまり、まだダイレクトレスポンスマーケティングを着手してない場合は、売上UPに繋がるヒントになるかもしれないので、本記事で紹介した手法の中でも貴社の着手しやすい手法から取り組んでみてください。