メルマガは古くからある媒体ですが、現代においてもBtoBの場面においてメルマガの力は衰えておらず、有効な方法です。
本記事では、メルマガの有効性や役割について触れたあと、効果を出すために知っておきたいBtoBメルマガの作成方法、運用方法などを解説します。メルマガの作成でお悩みの方はぜひご覧ください。
弊社のメルマガ運用事例についてまとめたダウンロード資料もございますので、下記からぜひご覧ください。
\【無料ダウンロード資料】研文社のメルマガ運用方法/
目次
メルマガとは?
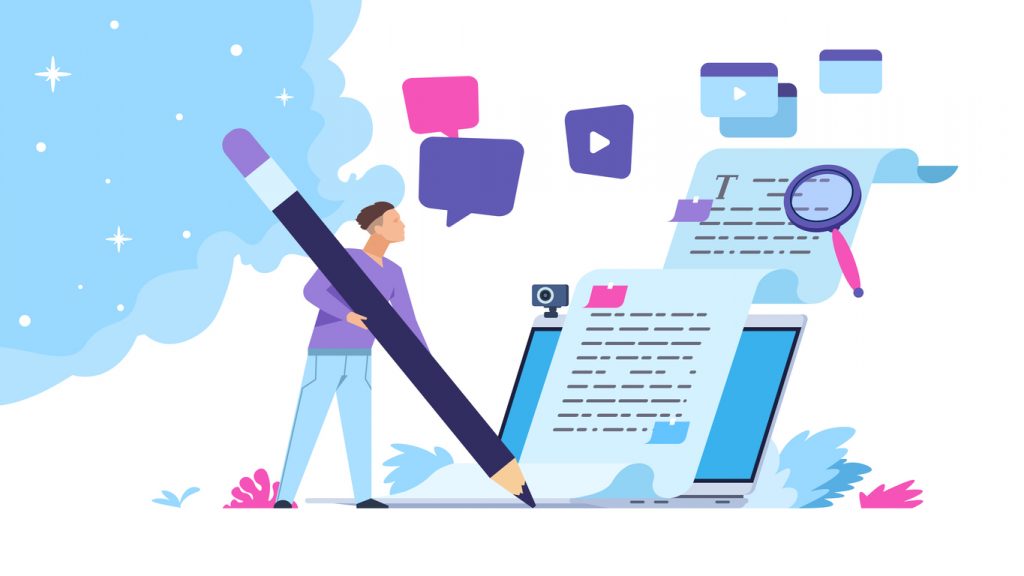
メルマガは、メールを使った情報発信手段です。主にダイレクトマーケティングの手段として活用され、登録された顧客のメールアドレスリスト宛にメールを一斉に配信します。自社の商品やサービスの宣伝、ノウハウなどの情報提供、キャンペーンやセミナー開催などの告知ができます。
企業にとって顧客とのコミュニケーションツールでもあり、定期的なメルマガの配信によって、顧客との接点を強化することが可能です。
一般消費者へ向けてメルマガを配信するときは、顧客のニーズや購入意欲を高めるような内容が主流ですが、BtoBでは自社の商材の費用対効果や顧客が得られる利益を伝えられるかが重要です。
BtoBにおいてメルマガが有効といわれる理由

BtoBにおいてメルマガが有効といわれるのは、企業間での接点を維持できる点にあります。日頃からメルマガで情報提供を行っていると、顧客企業側でニーズが顕在化したときに今まで築いてきた繋がりの分、他社よりもアドバンテージが得られます。
日本ビジネスメール協会の調査によると、ビジネスシーンで利用されるコミュニケーション手段はメールが最も多く、ほとんどの企業が少なくとも1日に1回はメールをチェックしています。近年、DXの推進やリモートワークの普及もあり、オンラインビデオ会議やチャット・メッセージングアプリを使ったやり取りも増加傾向にありますが、メールでのコミュニケーションには依然として需要があると考えられます。配信頻度にもよりますが、1日1回はメルマガを通じてコミュニケーションを取る機会があると考えてもよいでしょう。
(参照元:仕事で使うメールの利用実態を明らかに ビジネスメール実態調査2023)
BtoBはBtoCと違い、新しい商品やサービスの導入が決まるまでに多くのハードルがあります。例えば、社内稟議や他社製品との比較などです。BtoBの取引単価は高額な傾向があるため、投資額に見合ったリターンがあるのか、導入前に慎重に検討されます。メルマガを通じて関係を構築していれば、取引に繋がる可能性を高められます。
BtoBにおけるメルマガの役割

BtoBでのメルマガの役割は、主に顧客への継続的なアプローチ手段としての活用です。具体的には、以下の3つがあげられます。
情報を不特定多数の顧客に届ける
メールはビジネスシーンでのやり取りにおける手段のひとつであり、顧客がアクセスしやすい点も強みでしょう。加えて、低コストで配信できる点もメルマガの特徴です。
チラシ・DMなどの紙媒体、CMなどマスメディアの広告は出すたびに広告費・印刷費がかかりますが、メルマガは配信ツールの月額利用料のみです(クラウドタイプの場合)。月額利用料は配信規模に応じて変動し、一通あたりに置き換えると大抵は0.5~1円程度に収まります。
開拓先・休眠先から商談を創出する
メルマガは、商品やサービスに関心がある顧客や、ニーズがまだ顕在化していない潜在顧客に情報提供する役割があります。
休眠中の顧客とは、過去に商談などの接点があったものの購入には至らず、そのままの状態となった顧客のことです。どれぐらいの期間で休眠とみなすのかは企業によって異なります。
自社の商品やサービスに高い関心を持つ新規の見込み顧客がいる場合、メルマガによるリードナーチャリングで購買意欲を高められます。自社商品やサービスの紹介、導入事例、課題解決のノウハウなど、顧客に役立つ情報を提供し続けることで、自社商品やサービスに対する信頼度が高まる可能性があります。
見込み顧客が他社に流れてしまった場合でも、メルマガで定期的に接触していれば、サービスの乗り換え時に再度検討してもらえる可能性があります。顧客のニーズはいつ顕在化するかわかりません。機会を逃さないようにメルマガという媒体で定期的に接触することが大切です。
また休眠顧客化は、BtoBでの取引で起こりうる検討の長期化や、情報収集のみの接触にとどまってしまうなどさまざまな理由が考えられます。アプローチの際は休眠した理由を把握した上で行うのが効果的です。
■関連記事:リードナーチャリングとは?概要から手法までわかりやすく解説!
顧客にアップセル・クロスセルを案内する
アップセルとは、現在顧客が検討しているものや過去に購入したものよりもグレードの高い商品やサービスを提案し、購入を促すことです。クロスセルは、自社商品やサービスなどを購入した顧客や検討中の顧客に他のものも同時に検討してもらうことを指します。どちらも営業手法のひとつで、成功すれば顧客単価を上げることが可能になります。
メルマガ配信ツールには、クリック率などの数値を計測できる機能があるため、メルマガを読んだ顧客がどういう行動を取ったかをデータでチェックできます。データから顧客の行動や意欲、興味を把握し、購入の見込みが非常に高い顧客に絞ってアップセルやクロスセルを案内できます。メルマガと組み合わせて営業することにより、売上アップが見込めるでしょう。
効果の出るBtoBメルマガ作成のポイント

BtoBメルマガを成功させるために押さえておきたいポイントを5つ紹介します。
想定読者を明確にする
メルマガの想定読者(顧客像)を明確にしましょう。「〇〇業界向けの誰か」などの漠然とした設定ではなく、業種・企業規模・所属部署・役職・年齢といった顧客の状況や業務の悩み、どういうニーズがあるか、どこで情報収集しているかなどを具体的に考えペルソナを設定しましょう。
顧客像を具体的にすることで、ニーズを捉えた配信がしやすくなります。配信前に目的を定め、また、顧客が必要としない情報を提供するリスクを減らすため、配信前にメルマガの内容を具体的に決めておきましょう。
想定読者が開封したくなるタイトルを付ける
顧客がメールを開封するかどうかは、目に入ったときに思わず開きたくなるようなタイトルが重要です。内容がどれだけ有益な情報であっても、タイトルで読者に興味を持ってもらえなければそもそも読んでもらえません。
開封率が上がるタイトルを付けるには、「4Uの原則」(Useful(有益性)・Urgent(緊急性)・Ultra specific(具体性)・Unique(独自性))を意識しましょう。文字数は長くても30文字程度で、重要なキーワードは文頭に入れるようにします。また、端末の画面サイズごとに見え方が違うため、最初の15文字にアピールポイントを盛り込む工夫が大切です。
例えば、「期間限定」など緊急性を訴えるキーワード、「売上アップの秘訣」など顧客のメリットに繋がるキーワードはタイトルの頭に書きます。「〇〇する方法」「〇〇担当者は必見」など、ターゲットの業務に関連するキーワードを含めるのも開封率を高めるのに有効です。また、数字を含めると具体性が増すため、タイトルにインパクトが出ます。
本文冒頭で「有益な内容」であることを伝える
要件がすぐにわからないメルマガは、メールを開封してもらっても内容に興味を持ってもらう前に閉じられかねません。冒頭でどのような有益な情報が書いてあるのか伝えましょう。
自社商品やサービスに強く興味を持ってくれている場合を除き、顧客がメールの中身へ目を通す際に長い時間はかけません。ファーストビューで読むメリットが伝わる内容にしましょう
開封されるにもかかわらず顧客の反応が悪い場合は、これらを確認してみてください。
差出人名をなるべく営業担当にする
差出人名が企業名・メルマガ名だけだと、自分に関係がないメールだと認識される可能性があります。削除されたり迷惑メールに振り分けられたりしないよう、担当者名など顧客が見覚えのある情報を併記しましょう。
差出人名も受信ボックスで表示される情報のひとつです。タイトル以外に差出人の情報を工夫しても開封率が上がることがあるため、意識してみてください。
他には、顧客の名前を本文に入れ込むのもおすすめです。メルマガ配信ツールの機能を使えば、顧客の登録名を本文の中に差し込めます。顧客が受け取ったときにメルマガの内容がパーソナライズされているように見える効果があるため、積極的に活用してみてください。
見やすいレイアウトにする
メルマガで文章が長く続くと読みにくい印象を与えます。Webサイトで見出しタイトルと本文の見せ方が少し異なっているように、メルマガでも見た目のメリハリをつけると読みやすくなります。
例えば、記号・枠線で見出しと内容を区切る、箇条書きで情報を整理するなどの方法です。HTML形式のメルマガは画像が使えるため、ボタンを目立たせたり、商品イメージを画像で伝えたりできます。コードの記述が必要ですが、効果が大きいので活用してみてもよいでしょう。
前述の通り、上から順番に読まれるため、重要なコンテンツほど上に掲載するようにしましょう。資料請求などのCTAを設置する場合は、ファーストビューや本文の途中に適度な間隔で入れ込むのが効果的です。また、冒頭の下に目次を入れるのもよいでしょう。顧客がメルマガの内容をひと目で把握しやすくなり、気になる見出しがあれば中身に目を通すことも期待できます。
ただ、一回のメルマガに話題を詰め込むのは避けましょう。情報が多すぎると、どの内容が重要なのか顧客がわからなくなります。テーマはひとつに絞って配信するようにして、複数伝えたいことがある場合は、テーマごとに配信を分けるのがおすすめです。
\【無料ダウンロード資料】研文社のメルマガ運用方法/
BtoBメルマガ運用面で工夫すべきポイント

メルマガの運用にあたっては、送ったあとの効果測定と改善、効率化が大切です。以下では、5つのポイントを紹介します。
配信リストをセグメントにわける
メルマガ配信ツールにはセグメント配信機能があります。顧客の企業規模やこれまでの開封の有無など、さまざまな属性(セグメント)で顧客を分けることで、顧客の関心に合ったメルマガの配信が可能です。一斉配信と使い分けるようにしましょう。
セグメント配信が必要な理由は、顧客によりメルマガで求める情報のニーズも異なってくるからです。資料のダウンロードをするなど積極的なアクションがある顧客に対しては、タイミングを見て商品・サービスの紹介をすると購入に繋げられる可能性が高いでしょう。しかし、同じことを反応が薄い顧客に行うと逆効果になりかねません。
セグメントは、顧客の属性ごとに分けます。例えば、ニーズ・業種・職種・役職・勤務する会社の規模などです。他には、メルマガの内容で何をよく見ているのか、購入履歴の有無、問い合わせ回数などにも着目しましょう。担当者、マネージャー、経営者など、立場が違えば課題も異なるため、それぞれに合った内容を届けると好ましい反応を得られます。
A/Bテストを実施する
A/Bテストとは、パターンAと、一部の要素だけを変更したパターンBを提示・送付して、顧客からの反応を比べるテスト方法です。これは広告運用の改善などでよく活用される手法で、開封率が悪い場合や資料のダウンロードがあまりされない場合など、何らかの問題を改善したいときに行います。
「元原稿のAパターン」と「変更した原稿のBパターン」のメルマガを用意して、ランダムに配信します。顧客の反応を見つつブラッシュアップし、メルマガの効果を上げていきます。A/Bテストのデータの蓄積により、反応率が上がるキーワード、本文の書き方、話のネタ、顧客の課題が見つかることもあります。
A/Bテストをメルマガで試すとき、何が影響して効果が出たのかわからなくなるため、変更する部分は問題がありそうなひとつの要素のみとし、顧客の反応がどう変わるかを確かめます。その結果、どちらのパターンで開封率が高かったか、クリック率がよかったかなどの効果を測定してメルマガの改善に活かします。
毎配信で効果検証・改善を実施する
メルマガ配信ツールには開封率、クリック率などのデータを取得できる機能があります。開封率とは、文字通り開封されたメールの割合です。テキストメールでは対応できないため、計測したい場合はHTML形式で配信する必要があります。
クリック率は、配信できたメルマガのうち、どれだけリンクがクリックされたかの割合です。顧客がリンク先にどれだけ興味を持ったのかを計測するときに参照します。その他にも、ツール上ではコンバージョン率などさまざまな数値の確認が可能です。
IDEATECH社の運営する「リサピー®︎」において行われた、BtoBメルマガ担当者を対象とする調査によれば、メルマガの平均開封率は22%です。
(出典元:BtoBで有益なメルマガ配信とは?)
上記のデータを踏まえると、メルマガの開封率は、20%がひとつの目安と考えられます。下回る場合は改善の余地があると考え、タイトルの付け方や配信する時間帯などを見直してみてください。
ステップメールを実施する
ステップメールとは、特定の行動や条件を満たす見込み顧客に、決まったシナリオのメルマガを自動配信するマーケティング手法です。例えば、資料請求した顧客がいた場合、サンクスメールや次のアクションを促すメールを自動配信し、購買に至るまでのステップを段階的に案内していきます。最終目標は信頼度を高めつつ、購入・成約まで顧客を誘導することです。
見込み顧客の状況や関心に最適化したシナリオを設定することで、それぞれの顧客に合ったアプローチが可能です。購入までのシナリオを配信側で考える手間はありますが、一度設定し終わったら自動で配信されるため、リードナーチャリングを効率化できるメリットがあります。前述したメルマガの役割であるアップセル、クロスセルをシナリオに組み込むのもおすすめです。
電話やDMを組み合わせて実施する
複数のメディアを組み合わせる戦略をクロスメディアマーケティングといいます。デジタルメディアのメルマガと電話・DMなどのアナログメディアの組み合わせも同様です。媒体ごとの短所を補いつつ、長所を活かして販促・宣伝などができます。
メールは短時間で読まれる傾向があり、よほど興味がある場合を除いて熟読はされません。ところが、紙媒体になると結果が違います。DMの場合だと高い確率で開封されて読まれる傾向があります。
一般社団法人「日本ダイレクトメール協会」が行った「DMメディア実態調査2021」によると、自分宛に届いたDMを読んだ人は79.5%、自分宛以外でも52.9%の人が読んだという結果があります。DMを受け取ったことをきっかけに購入、問い合わせ、資料請求などのアクションを起こした割合は21.0%です。
(引用元:「DMメディア実態調査2022」調査報告書要約版)
BtoCを対象にした調査ではありますが、BtoBにおいても、顧客自身に関係するDMは読まれる可能性が高く、行動を喚起する効果が期待できるでしょう。
電話営業をする場合は、配信したメルマガの、開封率や資料請求、問い合わせなどの行動から購買意欲を分析しましょう。購買意欲が高い顧客にピンポイントで電話営業をすれば、相手も前向きに話を聞いてくれるでしょう。
■関連記事:ダイレクトメール(DM)とは?メリット・デメリットや効果をアップさせる方法も解説します!
おすすめの掲載コンテンツ

メルマガを作成するとき、どんなネタを掲載すればいいか悩んだことはないでしょうか。メルマガに書く内容でおすすめなものを以下で紹介します。ぜひ参考にしてください。
ブログ記事
ブログ記事を紹介することで、メルマガの顧客を自社メディアに誘導できます。既にブログで記事の定期更新をしている場合は特におすすめです。
ノウハウ記事などのお役立ち情報に触れてもらうことで、有益な情報を多く保有していると認識してもらえます。クリックひとつで気軽に閲覧してもらえるため、ニーズがまだ薄い潜在顧客への情報提供にも使えます。
メルマガに記載する記事への導入文は、タイトルと概要にとどめ、詳しい内容を知るためには記事をクリックしてもらうように導きます。紹介する記事は、特集や人気記事、顧客がよく抱えている悩みを解決できるような記事を取り上げましょう。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、潜在顧客へのアプローチに向いています。課題解決に至るノウハウの提供をしつつ自社商品やサービスの紹介もでき、認知度を高められます。
メルマガに掲載する際は、ひと目で何のコンテンツかわかってもらえるように、表紙画像や目次・概要などを載せておきましょう。手軽にダウンロードできることも添えておくとリンクがクリックされやすくなります。
また、メルマガ配信前に想定した読者のニーズにあった資料を配信することが重要です。購買意欲が低い段階の方に自社の商品やサービスをすすめるとマイナスの印象を与えかねないでしょう。
■関連記事:ホワイトペーパーとは?作り方や目的、注意点やマーケティングで活用する方法を解説!
導入事例
自社商品やサービスの利用を検討中の顧客には、導入事例を紹介してみましょう。BtoBの顧客は、費用対効果を検討してから購入を決めるため、メルマガで導入事例や利用者の声などを紹介すれば参考になるはずです。
紹介するときは、業界や課題など、顧客と共通点のある企業の成功事例を紹介するのがポイントです。導入後のイメージを掴んでもらうのに役立ちます。加えて、導入前の課題部分も記載するようにしましょう。共通の課題は共感に繋がるため、顧客に自分ごと化してもらいやすくなります。
既存顧客のインタビューや感想など、導入した顧客のリアルな声も紹介すれば、自社商品やサービスに安心感や信頼感を持ってもらえるでしょう。
セミナー・ウェビナー誘致
セミナー、ウェビナーの開催をメルマガで知らせるのもおすすめです。自分の課題を理解している、解決の必要性を感じている、既に自社商品やサービスに興味があるなど、購入意欲が高い顧客に向けた詳しい情報提供ができます。開催予定がある場合はメルマガで知らせてみましょう。
メルマガでセミナーの集客をする際は、テーマや開催日時などの基本情報を記載する他に、対象者のイメージを伝えるのがおすすめです。顧客が抱えている悩みや解決したい課題を言語化し、参加のメリットを提示することで、期待を持って申し込んでもらいやすくなります。
一通だけでは顧客がメールを見逃す場合があるため、お知らせは開催日までに複数回行ってもよいでしょう。
メルマガを効率的に運用するためのツール

メルマガは専用のツールを使って配信するのが一般的です。効率的な配信に便利なツールを紹介します。
メール配信ツール
メルマガ配信に必須なのがメルマガ配信ツールです。入力と誤送信を防ぐメールアドレスの登録機能に加え、メルマガ配信に欠かせない以下のような機能を利用できます。
- 会員登録/解除
- リスト管理
- HTMLメール作成
- 一斉配信
- 配信予約
- ステップメールの構築
- パーソナライズ配信
- 分析機能 など
これらに加え、迷惑メール判定を回避する仕組みも備えています。通常のメーラーで送るとスパム認定されやすいため、顧客のメールボックスまで届かないことがあります。確実に届けるためにも、メルマガの配信は専用システムを使うのがおすすめです。
ツールには無料と有料のものがあります。無料ツールは配信できる数に制限があるため、大人数に配信したい場合には向きません。無料から有料プランに移行できるツールも多くあります。初めは小さく始めて、会員が増えてきたら有料ツールに移るのも手です。ツールごとに機能は異なるため、必要な機能がそろっているものを選びましょう。
MAツール
MAツールとは、マーケティングの管理とリードナーチャリングなどの自動化ができるツールです。以下のような機能があります。
- 見込み顧客の行動履歴やアクセス回数などの顧客情報管理
- スコアリング
- コンテンツの配信機能
- メール配信機能 など
マーケティング施策を効率化できるツールで、CRMやSFAとの連携も可能です。ツールに蓄積したデータから確度の高い顧客を絞り込めるため、営業活動の効率がよくなります。
メルマガ配信ツールとの違いは、コストとメール配信に特化しているかどうかです。メルマガ配信ツールはメルマガ発行に必要な機能のみに絞られているため、シンプルに低コストで利用可能です。
一方、MAツールは、マーケティング業務を幅広くカバーできる機能がそろう分、コストがかさむ傾向があります。顧客分析機能が自社でどれほど活用できるかを考えて、必要であればメルマガ配信ツールと併用する選択肢もあります。
■関連記事:なぜBtoBでマーケティングオートメーションが必要なのか?具体的な活用方法や導入ポイントも解説
まとめ
チャットをはじめコミュニケーション手段が多様化していますが、ビジネスの場面において、メールは現在も使われているツールであり、顧客との接点を維持する欠かせない手段です。
ここまでご紹介してきたように、配信したメルマガを読んでもらうにはさまざまな構成上の工夫や、他のマーケティング手法とのシナジーが鍵を握ります。配信ツールの分析機能やA/Bテストを実施することで、配信ごとにブラッシュアップを重ねていくことができるでしょう。
\【無料ダウンロード資料】研文社のメルマガ運用方法/
以下の記事も参考にしてみてください。
