\全5回でお届けする「QCサークル活動」シリーズの第2回です。/
QCサークル活動を社内でスムーズに運営し、日常業務の品質と生産性を高めるには、正しい進め方と運営方法の設計が欠かせません。
第2回の本記事では、QCサークル活動の進め方や、運営方法を中心に、活動開始前の準備から計画立案・目標設定、課題選定・改善実行・振り返りまでのプロセスを、実務で使える手順とポイントに整理して解説します。
目次
QCサークル活動を始める前の準備
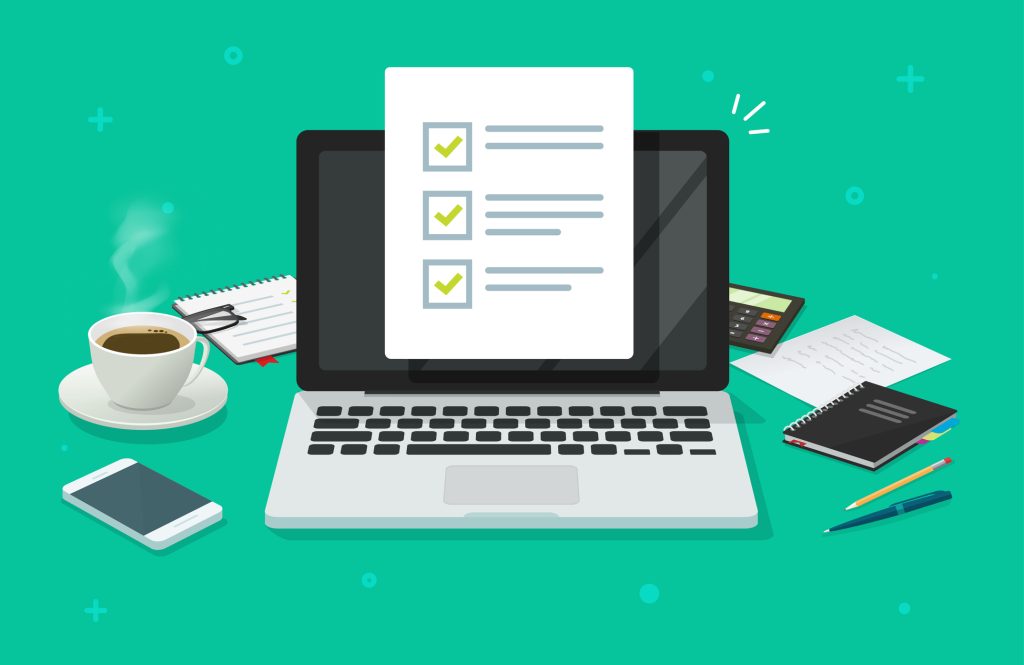
QCサークル活動を効果的に実施するためには、活動を指揮する人たちが事前に準備を整えることが重要です。この段階では、活動全体の方向性をある程度定め、グループが円滑に進められる環境を整えることが目的です。
活動テーマの選定
QCサークル活動を職場全体で効果的に進めるためには、活動を指揮する人たちが「全体の活動テーマ」をある程度示すことが重要です。このテーマ設定によって、各グループが取り組む課題がバラバラにならず、統一感を持って活動できます。また、職場の課題解決の優先順位を反映したテーマを設けることで、組織的な成果が得られやすくなります。
具体化したテーマにはせずに、各グループが活動の自由度を持ちながらも、組織全体の方針に沿った課題に取り組むことができるよう、大まかな枠組みを設定しましょう。
例)業務効率化、製品不良率改善、職場のコミュニケーション強化など
メンバー構成
QCサークルのメンバーは、職場の中で業務内容や現状をよく知る人材を中心に構成するのが効果的です。通常は5~10人程度の少人数グループとし、多すぎず少なすぎず適切な交流が図れる範囲にとどめます。また、異なる職務や経験のメンバーを組み合わせることで、多角的な視点から課題を捉えられるようになります。
QCサークル活動の具体的な進め方

QCサークル活動を成功させるためには、活動プロセスを明確にし、計画的に進めることが重要です。以下では具体的な手順を解説します。
活動計画の立案
活動計画は、QCサークル活動の道筋を定める重要なステップです。計画をしっかり策定すれば、メンバー全員が目的を共有し、効率的に活動を進めることができます。
計画の立案においては、まず活動の目的を再確認します。目的に基づいて具体的なスケジュールを作成し、必要なリソースを検討しましょう。計画にはどのような手法を使うか、メンバーの役割分担、実施のタイミングなど細かい内容を含めることが重要です。
役割分担
サークル内で明確に役割を分担することで、活動が組織的かつ効率的に進められます。例えば、以下のような役割を設定すると良いでしょう。
- リーダー:サークル全体の運営と調整を担当
- サポート役:リーダーを補佐し、進行や課題選定を支援
- 記録係(資料作成係):活動内容を記録し、成果を報告書としてまとめる
運営ルール
スムーズな活動を維持するためには、運営に関する基本ルールを明文化しておくことが重要です。例えば、以下のような項目を設定します。
- 活動頻度や時間(例:月2回、1回の活動は1時間以内)
- 活動方針や目的に従うこと
- 意見やアイデアを自由に出し合えること(批判禁止のルールを設定することで、心理的安全性を確保)
事前にこれらのルールが確立されていれば、活動中の混乱を防ぎ、メンバーが主体的に取り組める環境が整います。
課題選定
課題選定は、QCサークル活動の成果を決定づける段階です。適切な課題を選ぶことで、活動の方向性が確立し、メンバーの取り組みがより効果的になります。
課題は職場の問題点や改善点を基に選定します。まずは現在抱えている課題を洗い出し、あらゆる観点から優先順位をつけましょう。優先基準は、課題の重要度、緊急性、そして組織全体に与える影響などを評価することで決定します。
目標設定
目標設定はQCサークル活動の効果を最大化するために欠かせません。目標は活動の「羅針盤」として機能し、メンバーを統一した方向へ向けるのを助けます。そのため、目標は具体的かつ現実的である必要があります。
目標を設定する際には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
■具体性を持たせる
「業務を改善する」といった抽象的な目標ではなく、「製品不良率を半年間で5%削減する」など、具体的な指標を設定します。
■達成可能な範囲にする
高すぎる目標はメンバーのモチベーションを低下させる可能性があるため、現実的な範囲で設定することが重要です。
■職場課題とリンクさせる
目標が職場の課題や目指す方向性に合致していることを確認します。これにより、活動が組織全体にとって有益なものになります。
また、活動の初期段階では短期的な目標を設定し、成功体験を積むことをおすすめします。これにより、メンバーのモチベーションが高まり、さらなる挑戦に向けての意欲がわいてきます。
改善策の検討
次は解決策を検討します。この段階はQC活動における中核的な部分であり、メンバーの協力が欠かせません。改善策の検討においては、まず自由な意見交換の場を設けます。ブレーンストーミング(Brainstorming=集団でアイデアを出し合うこと)を活用することで、メンバーそれぞれの視点から多様なアイデアを引き出すことができます。
集まったアイデアを評価し、実現可能性や効果の大きさに基づいて優先順位をつけます。選ばれた改善策については、具体的な実現方法や必要なリソースを詳細に検討し、実際にどのように試行するかを明確にします。
実行計画の実施
検討された改善策が決まったら、実行計画を立て、それを現場で実施します。実行計画は、改善策を具現化するための具体的なステップを示したものです。
まず、改善策を試行するスケジュールを設定し、担当者を割り振ります。また、実施の進捗を管理するためにチェックリストやモニタリングの方法を明確にします。実行計画をすべてのメンバーと共有し、理解を深めたうえで作業に取り組むことが重要です。
実施段階では、計画通りに進むかどうかを随時確認し、問題が発生すればその都度調整を行います。現場での試行を通じて得られたデータは、次の振り返り段階で活用します。
振り返りと共有
活動が一通り終わったら、振り返りを行い、成果や課題を共有することで、次のステップへつなげます。このプロセスは、活動全体の学びを深めるうえで非常に重要です。
振り返りでは、計画通りに進んだ部分と問題があった部分を明確にします。PDCA(Plan=計画、Do=実行、Check=検証、Action=改善)のサイクルを活用し、次回の活動に向けた改善点を整理します。このプロセスを通じて、QCサークル活動の品質向上を図ることができます。
また、活動の成果や学びをメンバー内で共有するとともに、組織内で報告します。共有を通じて職場全体の改善意識が高まることで、QC活動の効果がさらに広がります。
研文社が取り組むQCサークル活動の運営ポイント

研文社の取り組みとして「メンバー選定」「進行管理」「職場全体への情報発信」という3つの側面から、当社が行っているQCサークル活動の運営方法のポイントを紹介します。
活動自体は業務の一環として行っているため、就業時間内に活動しております。
メンバー選定
QCサークル活動の核となるのが、適切な人材の選定です。研文社では、メンバー選定が活動の成果を左右する重要なプロセスであると考えています。
まず、メンバーは日常的に同じ業務を行っている部署の人たちを中心に各グループ5~10人で構成しています。部署によっては大人数になるケースもあるのでその場合は2チームに分けるなど柔軟な編成をしています。
この選定方針は、品質改善や業務効率化といったテーマで活動を進める際に、課題に対する認識のズレを最小限に抑え、自分ごととして取り組む姿勢を自然に醸成できるというメリットがあります。同じ業務に携わっているメンバーで構成することで、その後の業務改善に直結しやすく、成果の実現性が高まるだけでなく、活動の進行を円滑にする効果も期待できます。
分野や職務が異なるメンバーも加えることで多角的な視点を取り入れることもひとつの方法ですが、研文社では、関連性のある業務に携わるメンバーで構成することが、より具体的な改善提案や実行につながりやすいと考えています。
進行管理
計画的、継続的に進行を管理することで、効率的な活動を維持しています。
研文社のQCサークル活動において、進行管理は品質管理部門が中心となって進めています。活動を円滑に進めるためには、リーダー的な存在が必要であり、品質管理の部門がその役割を担う形をとっています。この部門が進行管理の軸となることで、活動の統制が取りやすくなり、効率的な運営が可能になっています。
具体的には、各グループの進捗状況を定期的に把握するために、月ごとの定例ミーティングを実施しています。このミーティングでは、各グループが活動内容や進捗状況を報告し、課題や状況の共有を行います。これにより、グループ全体の活動が計画通りに進んでいるかを確認するとともに、必要な調整や改善を適宜行う仕組みを整備しています。
職場全体への情報発信
研文社では、QCサークル活動を単なる個々のグループの取り組みにとどまらず、職場全体にその成果と学びを共有することを重視しています。
その取り組みとして、「活動報告会」を年に一度開催しています。この報告会は、各グループが取り組み内容や改善結果を職場全体に発表する場であり、他のグループの活動内容を聞くことで、会社全体での改善意識が高まり、品質向上や業務効率化といった目標に対する取り組みが職場全体で進められるようにしています。
さらに、報告会では社員による評価制度を導入しており、発表内容に対して「改善効果」「実効性」「発表のわかりやすさ」といった指標を基に総合得点を算出しています。評価に基づき優れたグループを表彰し、1位には賞金を授与することで、各グループの振り返りと改善意識を促進するとともに、活動へのモチベーションを高める仕組みを整えています。
まとめ
QCサークル活動は、職場の品質向上や業務効率化を実現するために効果的な手法です。成功の鍵は、活動開始前の準備から計画・改善・振り返りまでを体系的に進めること、そしてメンバー選定や進行管理、情報共有といった運営体制を整えることにあります。研文社では、活動報告会や評価制度など独自の仕組みを導入し、組織全体にカイゼンの効果を波及させる取り組みを行っています。
次回(第3回)では、QCサークル活動を行う際の問題解決手法「QC7つの道具」ついて詳しく解説しますので、ぜひご期待ください。
■関連記事
